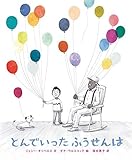ネタバレを気にするかどうか?で分かれる記憶タイプの違い・・・
あら!私ネタバレ積極的に見るタイプかも!!(笑)
最近Youtubeでも読書レビューというか完全に内容のまとめ(オリラジあっちゃんの本紹介とか完全に中身の再話だよね?)の動画がたくさんあるけど、あーいうの大好き。それ見たうえで、本買ったり映画見に行ったりすることが多い。
「記憶」に関して、 『都市と野生の思考』で紹介されていた、E・M・フォスターという作家の言葉がおもしろかった。
「記憶」というものは若い間はクロノジー(時系列にまとめられたもの)で、中年以降はパースペクティブなもの(遠近法)になる。そして老後はピクチャー、一枚の絵にまとめられ、死んだら順序も絵もバラバラに分散してしまうんだ、って。
記憶力は衰える、ってのがワレワレの「常識」なわけだけど、いやいや、「記憶」の様相というかあり方が変わってるだけなんだ、って思えばそれはそれでステキよね。
ちょうど先日読んだこの絵本も、おじいちゃんとぼくの記憶(思い出)のハナシだった。おじいちゃんの風船は、とんでいっちゃうんだけど・・・。
じいちゃん、ってキーワードが出たら絶対に思い出す夢がある。
思い出の風船は飛んで行ってしまったように見えるけど、人は人との関わりを通して、実は誰かに手渡されていたりする。
おじいちゃん(おばあちゃん)と孫、って関係性は結構人間社会の中でダイジなんじゃないかって思ったのは、上の『都市と野生の思考』を読んでても思った。
文化(価値観の土台)は隔世で引き継がれていく。
って法則も、わかる。
民俗学的にも、子どもと老人は「常識」の枠外にいる存在だから、社会のトリックスター的なポジションだよね。あっちがわとこっちがわのあわい境界線上にいるってのがミソ。
そういう向こう側の「老人」がいたから、じいさんばあさんは昔は子供にも大人にも尊敬され一目置かれる存在だった・・・んだけど、最近は「いつまでも現役」を掲げてギラギラした老人がいて、子どもも小さい大人になることを強いられる。
均質化って、どっかでやっぱりヒズミが出ちゃう。
「記憶」といえば「知識」についてもオモシロイはなしがたっくさん集まってきたからそろそろアウトプットしたい。。。
なにを記憶する(覚えている)のか、って結構アイデンティティ(Who am I?)に関わることよね。
Any day spent with you is my favorite day.
So, today is my new favorite day.
モノも記憶(知識)も「Nothing(なーんにもない)」子どもと老人って、弱い。でも、だからこそ、いちばん尊くて強い存在なのかも。
★ 記憶の不思議に関する過去記事
★語学で使える記憶術に関する過去記事